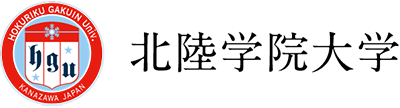Interview
先生が専門分野を学ぶようになったきっかけ、出会いエピソードをおしえてください
私の専門分野は保育と育児の異文化比較研究です。私はアメリカで24年間過ごし、子育て、保育者、大学教員を経験してきました。アメリカの多様な文化背景を持つ人々と接する中で、保育、教育、育児に対する異なる考え方に関心を持ち、異文化比較研究を進めてきました。また、私は定型発達児とは異なる特性を持つ子どもたちの教育にも関心をもっています。アメリカで、私の息子が自閉スペクトラム症と診断され、娘はギフテッド教育を受けてきました。これらの経験を通じて、育児の喜びと同時に困難やストレスも多く体験してきたため、親のメンタルヘルスを向上させる方法についての研究にも取り組んでいます。

Interview
専門分野の面白さはどんなところですか
現在、アメリカの医科大学に客員研究員として所属しています。そのため、さまざまな国籍を持つ研究者と共同で研究を行っています。また最近では、日本の保育研究チームとも協力し、アメリカだけでなく中国やスウェーデンなどの保育者にインタビューを行いながらデータを収集しています。当たり前だと思っていた習慣や考え方が覆されることもあり、自分の思考が刺激されるのが面白いです。
Interview
ゼミの進め方や特徴などを教えてください
私は学生が「面白い」と感じ、「やってみたい」と思うテーマに出会い、最終的には「やり遂げた」という達成感を得られるよう、柔軟でありながらも厳しい指導を心がけています。特に授業のテンポを変えることで、生徒の関心を惹き続けることが大切だと考えています。単調な進行は学生を退屈させてしまうため、私の授業では「意外性」「柔軟性」を取り入れ、楽しく充実した学びの場を提供することを目指しています。

Interview
地域の課題と学びがどのようにつながっているかを教えてください
これからの日本の将来を考えると、保育の質を高めることは最優先事項です。私の場合、異文化比較というフィルターを通して、日本の保育の質を高めることに貢献したいと思っています。また発達障害児、ギフテッド児とその家族は、通常以上に悩みを抱える場合が多いのですが、適切な相談相手が見つからないことが多いです。私のところにも、時々相談が寄せられています。このようなさまざまな特性を持つ子どもたちやその家族が生きやすい社会を築くため、学生たちにも多様性を重視する視点を身につけてもらうことを目指して教育活動を行なっています。
Interview
大学生に学んでほしいこと、アドバイスなどをお願いします
アメリカの大学でダイバーシティ(多様性)の授業を教えていた時、「Get out of your comfort zone!」(精神的に楽で慣れ親しんでいる不安のない範囲から外に出て、リスクを負って新しいことにチャレンジしなさいという意味)と伝えてきました。日本のみなさんにも同じことを伝えたいです。人生は一度しかないです。失敗を恐れずに大学や学外でいろいろな人と出会い、体験を積み重ねてください。失敗を重ねる中で、人と違う「自分らしさ」や「自分の強み」をぜひ本学で発見していただけたらと願っています。