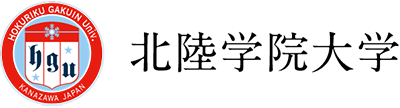教員紹介
教育学部 幼児教育学科
-

-
まつもと りさ
松本 理沙
准教授
| 保有学位 | 博士(社会福祉学) |
|---|---|
| 専門分野 | ・社会福祉学 |
| 担当科目 | 子ども家庭福祉論Ⅰ・Ⅱ、家庭支援論、社会的養護内容、子どもと法、保育実習指導Ⅰ・Ⅲ(施設)、保育実習Ⅰ・Ⅲ(施設)、キャリアデザインⅠ、プロゼミA、専門ゼミⅠ・Ⅱ、卒業研究 |
| 研究のテーマ | ・障害児者のきょうだい支援 ・ケアラー支援 |
| 研究内容 | 障害のある家族をケアする人たちへの支援に関する実践・研究に取り組んでいます。特に、障害児者の「きょうだい」(障害のある兄弟姉妹がいる人)への支援に関する実践・研究に携わっています。 |
| 研究内容のキーワード | きょうだい、ヤングケアラー(子どもケアラー)、若者ケアラー、アダルトチルドレン、セルフヘルプ・グループ、ピアサポート |
| 一言コメント | 保育・教育の現場では、目の前の子どもだけでなく、背景にある「家族」についても考える必要があります。担当科目等を通して、「家族」を考えるための基礎知識もお伝えできればと思います。 障害児者のきょうだいやケアラーが自分の体験を安全に語るための場づくりや、支援の必要性を訴える啓発活動等にも取り組んでいます。ご関心のある方は、お声掛け下さい。 |
研究業績
著書
|
『子ども・若者ケアラーの声からはじまる ヤングケアラー支援の課題』 |
共 著 | 2022(令4)年3月 | クリエイツかもがわ |
学術論文
| 『ヤングケアラー支援の実践―障害児者のきょうだい支援の事例から』 | 単 著 | 2023(令5)年4月 | 『教育と医学』第71巻第3号 |
| 『ヤングケアラーの啓発のあり方に関する研究―中学生の調べ学習における成果発表の分析から―』 | 単 著 | 2024(令6)年3月 | 『北陸学院大学・北陸学院大学短期大学部 研究紀要』第16号 |
その他
| ヤングケアラーの実態、支援者の心構え | 2023(令5)年6月 | 加賀市市民健康部子育て支援課主催 ヤングケアラー支援者向け研修会 | |
| 現在(いま)を生きるきょうだいの思いとは | 2023(令5)年6月 | 一般社団法人京都府自閉症協会きょうだい部主催 きょうだいセミナー2023 | |
| 障害児者の“きょうだい”として いま、ご家族に伝えたいこと | 2023(令5)年7月 | ジェイアイシーセントラル株式会社セミナー | |
| ヤングケアラーを理解するためのヒント | 2023(令5)年7月 | 北陸学院中学校ミッション祭「幼き介護者〜深めようヤングケアラーへの理解〜」(事前準備) | |
|
ヤングケアラーとは ~子どもが子どもでいられる街~ |
2023(令5)年7月 | 石川県青少年育成推進指導員連絡会、石川県主催 令和5年度石川県青少年健全育成南加賀ブロック会議 | |
| ヤングケアラーの理解と支援 | 2023(令5)年8月 | 石川県教育委員会主催 令和5年度スクールカウンセラー等・スクールソーシャルワーカー連絡協議会 | |
| ヤングケアラーを正しく知ろう | 2023(令5)年8月 | 金沢市主催 「ヤングケアラーを正しく知ろう」講演会 | |
| ヤングケアラーについて | 2023(令5)年8月 | 石川県教育委員会主催 ヤングケアラー講座 | |
| ヤングケアラーの現状といま私たちができること | 2023(令5)年10月 | 小矢部市社会福祉協議会主催 小矢部市社会福祉大会 | |
|
身近な地域で気づく、寄り添う、支える ~ヤングケアラーとは~ |
2023(令5)年11月 | 富山市、富山市社会福祉協議会主催 富山市福祉フェスティバル2023 | |
|
子ども・若者ケアラー支援 ~家族ケアラーの声から学ぶ~ |
2023(令5)年12月 | 一般社団法人石川県医療ソーシャルワーカー協会主催研修会 | |
|
障害のある人のきょうだい ヤングケアラーを考える |
2024(令6)年1月 | Sibkotoシブコト主催シンポジウム(助成:公益財団法人キリン福祉財団、後援:石川県・金沢市・石川県社会福祉協議会・金沢市社会福祉協議会、ほか) | |
| 当事者・支援者の立場から見つめ、考えるヤングケアラーの支援 | 2024(令6)年2月 | 富山県主催 令和5年度第2回ヤングケアラー関係機関職員研修会 | |
| ヤングケアラーとは | 2024(令6)年2月 | ゲートキーパーネットとやま主催 2024年ゲートキーパー交流会 | |
| 「金沢版ヤングケアラー支援マニュアル」作成の関与 | 2023(令5)年度 | 金沢市ヤングケアラー支援に関する検討会 | |
| 「ヤングケアラー特設Webサイト」監修 | 2023(令5)年度 | 石川県 | |
| 「『きょうだい児』について知ろう」指導者 | 2023(令5)年度 | 石川県健民運動推進本部「子どもの夢実現サポート事業」 |