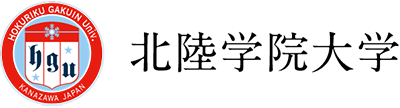地域教育開発センター
事業報告(地域教育開発センター)
事業報告 情報
地域教育開発センター活動報告書のご案内
2025/06/16 (月)
地域教育開発センターでは、地域の皆さまを対象とした各種講座を実施してまいりました。
これまでの講座の実施状況や参加者の声などをまとめた報告書を、下記のとおり掲載いたします。
2022年度・2023年度の報告書についても、これまで掲載が遅れておりましたが、このたびあわせて公開いたしました。
ぜひご覧いただき、地域づくりや学びの振り返りとしてご活用ください。
また、報告書の後半では、学生が主体となって地域と関わる活動の方向性や実践についても紹介しております。
講座事業は企画見直しのため中止いたしますが、学生による地域貢献活動は今後も継続されていく予定です。
引き続き、あたたかいご支援を賜りますようお願い申し上げます。
【報告書一覧】
2024年度活動報告書(PDF)
2023年度活動報告書(PDF)
2022年度活動報告書(PDF)